トラブル対応が続き、押しつぶされそうなあなたへ。
「またクレームがきた」
「ヒヤリ・ハットが減らない」
「職員がミスを恐れて挑戦しなくなった」……。
でも、そんなあなたにこそ、知ってほしいトラブルを寄せ付けない視点があります。
それは、“失敗やクレームは職場を良くするチャンスだ”という考え方です。
今回は、西田文郎氏のネガティブな出来事をポジティブに転換する「勝負脳」の習得法をお伝えしていきます。
「これはチャンスだね」が空気を変えるリーダーのひと言
前回は、『「どうせ無理」口ぐせ変換術』という使う言葉を変えることで介護現場の空気が激変する方法をお伝えしました。
今回は、西田文郎氏の著書『勝負脳の磨き方』をベースに、クレームや事故を“改善のチャンス”に変える脳のつくり方です。
結論から言うと、クレームや事故が起きたときに『これは改善のチャンスだね』と捉えられるリーダーがいるチームでは、自然とクレームや事故が減っていくのです。
また、そんな考え方のできるリーダーがいるチームは、メンバーの尊敬と信頼をも集められるんです。

ピンチのときこそ問われる“脳の使い方”
なぜ、そう言い切れるのでしょうか?
人はピンチに陥ったとき、その場の感情に流されがちです。
とくに介護現場では、ミスや事故が命に関わることもあるため、感情的になってしまうのも無理はありません。
ですが、そこでリーダーが「これは学びの機会だ」と冷静に言えると、チームに落ち着きと方向性が生まれます。
これは脳科学的にも裏付けがあります。
脳はストレスを受けると、“扁桃体”が過剰に反応し、論理的な判断を司る“前頭前野”の働きが鈍くなります。
そのとき、自分自身に『これはチャンス』とポジティブな認知を与えてやります。
そうすると、前頭前野の働きが保たれ、建設的な判断ができる状態を作るのです。
むずかしい理論はさておき、周囲が声をかけづらくなるような雰囲気で怒鳴り散らしているリーダーには誰も近づきたがらないですよね。
信頼を寄せるどころか相談もしたくないものです。
職員はリーダーの“表情”と“言葉”に実に敏感です。
よく、人の顔色をうかがう、とも言います。
「どうしてこんなことに…」とため息をつく上司より、
「この経験を活かそう!」と声をかけてくれる上司のもとで働きたいと思うのは当然です。
つまり、「勝負脳」とは、ピンチのときほど冷静に、
前向きに“意味づけ”できる脳の使い方なのです。
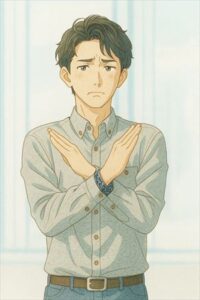
実例で見る「勝負脳」が職場を変えた瞬間
イメージが湧きにくいかもしれませんので、事例を紹介します。
◆ 事例①:ミスをチーム力向上のきっかけに
あるデイサービスの現場で、新人職員が食事介助中に誤嚥を誘発しそうになるミスがありました。
その場にいたリーダーは、すぐに状況を収めたあと、こう言いました。
「誰にでも初めてはある。
でもこの経験が、チーム全体の対応力を高めるチャンスになるよ。」と。
その言葉に、新人職員は泣きながらも「これからはもっと注意して頑張ります」と前向きになれたことは言うまでもありません。
ここで、「何でそんなことも出来ないの?」と怒鳴られていたらどうでしょうか?
考えるまでもないですよね。
そんなリーダーだと、周りにいる客様も声をかけづらくなります。
その後、食事介助に関する簡易マニュアルが職員の案で作られ、現場の意識が大きく変わりました。
クレーム対応が信頼アップにつながる
もう一つの例として、クレーム対応の現場を見てみましょう。
訪問ヘルパーを利用されているお客様から
「時間通りに来てくれない」とのクレーム。
リーダーはまずそのお客様に謝罪と共感を伝えたうえで、職員にはこう言いました。
「この声を活かして、私たちの連携を強化しよう」
その後、出発前確認やLINE WORKSでの共有体制が整備され、遅延は激減。
クレームがあったご利用者からは「最近すごく良くなったね」と逆に褒められるように。
先ほどの事例と同様、感情が先に立ってしまい「なんで遅れたの!」と職員に怒鳴ったところで、遅延はなくならないでしょう。
原因究明も必要ですが、中にはどんなにイライラしても、クレームをつけないご利用者もいらっしゃいます。
リーダーの発する言葉一つでメンバーの意識も変わり、チームで対策を考えられるように自然にメンバーも自分たちで考えて意見を出せるような雰囲気が作られていきます。
メンバーが働きやすい環境を作ること。
それがリーダーの役割であり、クレームや事故も遠ざけるのです。
もしあなたが今の職場で「もう限界かも」と感じているなら、
それは“成長のサイン”かもしれません。
環境を変えることで、自分らしく働ける場所に出会えることもあります。
勝負脳を育てる3つの実践トレーニング
「勝負脳」は、トレーニングで育てることができます。
以下の3つの方法を実践してみましょう。
① 起きた出来事に「肯定的な意味づけ」をする習慣
・「なんでこんなことに…」→「これを糧にするにはどうする?」
・「運が悪い」→「逆に、今ここで気づけてよかった」
② クレーム・事故報告書に「チームの気づき欄」を設ける
・個人の反省だけで終わらせず、チームとして何を学べたかを書く
・会議では「責める」のではなく「共有と成長」を目的とする
③ 朝礼や終礼で「前向きな問いかけ」をする
・「今日はどんな成長があった?」
・「次に活かせそうな気づきは?」
これにより、職員の“考える力”が育てられるとともに
「やればできる!」という達成感。
「これなら自分にもできそう」という自信が生まれます。
リーダーが「勝負脳」でいることで、現場全体が「学び続ける職場」に変わっていくのです。
こんなチームになれば、サブリーダーも自然と育っていくことでしょう!

まとめ
何で介護の現場で「勝負脳」?
と思われた方も多いでしょう。
事故やクレームがゼロの職場はありません。
でも、それをどう捉え、どう行動するかで、未来は大きく変わります。
「これはチャンスだね」——この一言を口にできるリーダーこそ、チームの尊敬を集め、信頼を築く人です。
あなた自身がまず「勝負脳」を手に入れることで、現場の空気が変わります。
そしてその積み重ねが、ご利用者・家族からも信頼される、最強の介護チームをつくる土台になるのです。
次回は、「「スタッフが動かない」はリーダーの言葉で変わる|影響力の正体とは?」という話題をお届けします。
コメント