その「辞めたい気持ち」はあなただけじゃない
こんにちは。ゆるちょこです。
「もう限界・・・・リーダーなんて引き受けなければよかった…」
介護主任やリーダーを任されて、そう感じたことはありませんか?
現場の責任、スタッフ育成、利用者対応、家族への説明…業務は多岐にわたり、常に板挟みの立場に置かれるのがリーダー職。
実際、私も何度も「辞めたい」と思ったことがあります。
しかし、この「辞めたい」という気持ちは、決して弱さではなく「成長のサイン」であることをご存じでしょうか。
この記事では、私自身の体験談や同僚の失敗談を交えつつ、「カッツ理論」を軸にリーダーの悩みを整理し、前向きなキャリア形成につなげる方法を解説します。

介護リーダーを辞めたいと感じる瞬間とは?
• 「責任が重すぎて辞めたい…」
• 「人間関係のストレスに耐えられない」
• 「部下育成やシフト管理がつらい」
リーダーの役割は、現場を支える要である一方で、強いプレッシャーや孤独感を伴います。
「もう辞めたい」と感じても、それはあなたが弱いわけではなく、介護業界の構造的な課題やスキル・環境の不一致から来ているケースがほとんどです。
責任の重さに押しつぶされそうになる
私が主任をしていた頃、最もつらかったのは「シフト調整」。
一人欠けると現場は大混乱、利用者対応まで自分に集中し、毎晩ぐったり…。
その時期は「辞めれば楽になるのでは」とまで思いました。
人間関係をこじらせた同僚のケース
ある同僚リーダーは、スタッフ間のトラブルに強く介入しすぎて逆に不信感を招き、最終的には孤立して退職。
介入の仕方を誤ると、チーム崩壊につながることを目の当たりにしました。
キャリアの先行きが見えない
「このまま同じ職場にいても成長できないのでは?」と将来に不安を感じる瞬間も多いでしょう。
頑張っても評価されない環境にいれば、辞めたい気持ちが強まるのは自然です。

カッツ理論で整理するリーダーに必要な3つのスキル
組織論で有名な「カッツ理論」では、管理職に必要なスキルを以下の3つに分類しています。
これは、ハーバード大学のロバート・カッツが提唱した管理職スキル理論ですが、介護リーダーにそのまま当てはまります。
- テクニカルスキル:介護技術や制度知識などの専門スキル
- ヒューマンスキル:人間関係を築き、信頼を得る力
- コンセプチュアルスキル:現場を俯瞰し、課題を整理・判断する力
「辞めたい」と思う背景には、これらのスキルのどこかに不安や不足を感じているケースが多いと言われています。
下記の図を参照しながら順に説明を進めていきたいと思います。

不足スキル別の改善策
テクニカルスキル不足の場合
• 資格取得(介護福祉士・ケアマネなど)で自信をつける
• 勉強会や研修で最新知識を習得する
ヒューマンスキル不足の場合
• 定期的に1on1でスタッフと向き合う
• アサーティブ・コミュニケーションを学ぶ
コンセプチュアルスキル不足の場合
• 上司やエージェントに相談し、外部の視点を得る
• 現場の課題を「見える化」して整理する
何でも自分でやろうと思うと、起こっている課題を整理したり、問題の本質を見極めて優先順位をつけられなくなってしまいます。
つまり、問題解決ができない、業務効率や生産性が上がらない、部下が育たない、チームワークが醸成されないという負のスパイラルに陥ってしまいます。
介護リーダーがスキルを伸ばす5つのステップ
- 自己分析で強みと弱みを把握する
- 学習目標を短期・長期で設定する
- 現場で小さな改善を実践する
- メンターや経験豊富な上司から学ぶ
- 成功体験を積み重ね、自己効力感を高める
👉これを繰り返すことで「リーダーを続ける自信」を取り戻す人も少なくありません。
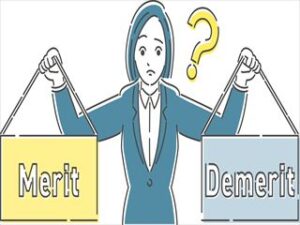
それでも辞めたい…転職を考えるときのポイント
「改善を試みても、もう限界…」というときは、転職を前向きな選択肢として考えることも大切です。
今の職場に留まるか、転職すべきかの判断基準
- 頑張っても評価されない
- 残業や休日出勤が常態化している
- 人間関係の改善が見込めない
これらに当てはまる場合、環境を変えることが最善策になることもあります。
<※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。>
転職エージェントを活用するメリット
-
- 非公開求人を紹介してもらえる
- 年収交渉や条件改善を代行してくれる
- 現場経験を理解したコンサルタントに相談できる
現場改善のために日々努力していても、
「このまま今の職場で頑張るべきか…」
「それとも、もっと自分が成長できる環境へ踏み出すべきか…」
と悩むことはありませんか?
そんなときは、介護職専門の転職エージェントに相談するのがおすすめです。
介護業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたの経験や強みを理解したうえで、
最適な職場やキャリアプランを一緒に考えてくれます。
👉 介護職キャリアサポートはこちら今すぐチェック|あなたに合う介護職求人を見る
まとめ|「辞めたい気持ち」を前向きなキャリアの第一歩に
介護リーダーとして辞めたいと感じるのは、責任感が強く、現場に真剣に向き合ってきた証拠です。
大切なのは、その気持ちを「逃げ」ではなく「未来を変える一歩」と捉えることです。
資格取得やスキル強化で自信を取り戻す道もあれば、環境を変えてもっと輝ける場所を見つける選択肢もあります。
コメント