「やりがいのある職場」を作ろうとすれば、必ず組織の変化が必要となります。
そして変化には必ず「抵抗」がつきまといます。
主任や管理者として新しい仕組みを導入したいと思っても、「今までのやり方で十分だ」「余計なことはやめてほしい」といった声に阻まれることは珍しくありません。
特に40代以降の介護リーダーは、自身のキャリアアップや転職の可能性も視野に入れながら、「現職で改革を進めるべきか」「新しい職場で挑戦すべきか」と迷うことも多いのではないでしょうか。
前回(第4話:介護現場で離職を防ぎ、職員が長く働きたいと思う職場づくり)では、やりがい・働きやすさ・成長機会の三本柱を整えることが職員の定着率向上につながることをお伝えしました。
今回は、ただ抵抗を避けるのではなく、抵抗を“味方”に変えて進む方法を知ることが、リーダーとしてもキャリア形成においても重要になるというテーマでお届けします。
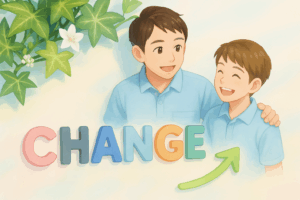
抵抗は自然な現象 ― ドラッカーが説く変革の本質
ピーター・ドラッカーは『マネジメント[エッセンシャル版]』(ダイヤモンド社)でこう述べています。
「変革は人々の習慣や安心を揺るがすため、必ず抵抗を伴う」
つまり、改革に抵抗が生じるのはリーダーが下手だからではありません。
抵抗は自然な現象であり、むしろ健全な組織の証ともいえます。
問題はその抵抗をどう扱うか。
敵として排除するのではなく、理解し、活用することで変革は推進力に変わります。

抵抗の正体は「不安」である
多くの職員が改革に抵抗を示すのは、実は「不安」が根っこにあります。
例えば、職員は次のように感じます。
- 自分の仕事がなくなるのではないかという恐れ
- 新しいやり方についていけるかという焦り
- 変化の目的が分からないことによる不信感
こうした不安は、情報不足や心理的安全性の欠如から生まれます。
私の体験談:老健でのシステム変更
私が40代で老健の主任を務めていた頃、介護記録のシステムを刷新したいと提案しました。
ところがベテラン職員からは「私たちには無理」「紙の方が安心」と強い抵抗が返ってきました。
そのとき私は「いきなり完璧に覚える必要はない」「困ったらいつでも聞いていい」と伝え、短時間の学習会を繰り返しました。
結果的に「思ったより簡単だった」「利用者さんと関わる時間が増えた」と前向きな声が出始め、不安は和らぎました。
抵抗をゼロにすることはできませんでしたが、安心感を与えることで改革が前に進んだのです。

説明不足は反発を生む ― 「上が勝手に決めた」と思われないために
抵抗を強める最大の要因のひとつが「説明不足」です。
介護現場は多忙だからこそ、突然の改革は「余計な仕事を押し付けられた」と感じやすいのです。
私の体験談:送迎ルート変更の反発
デイサービスで送迎ルートを変更したときのことです。
スタッフからは「利用者さんに負担がかかるのでは」「ただ効率化のためだろう」と不満が噴出しました。
私はそこで「利用者の安全確保と送迎時間の短縮が目的」であることを丁寧に説明し、さらに現場の意見も取り入れました。
スタッフは、どうしても今までのやり方や、時間短縮だけのために都合よく送迎ルートを考えがちです。
とはいえ、道路事情や利用者の体調といった細やかな情報は現場スタッフが一番知っています。
その声を反映させたことで、「納得できる変更」へと変わり、反発は次第に収まりました。
ドラッカー流「変革推進」の3つの条件
ドラッカーは『イノベーションと企業家精神』(ダイヤモンド社)で、変革を成功させる条件を次の3つにまとめています。
- 目的を明確にする
- 小さく始める
- 成果を早く見せる
介護現場では、いきなり全体導入するのではなく、一部ユニットや小さな業務から試すことが効果的です。
成功事例 ― 抵抗を推進力に変えた介護現場
老健の事例:ユニット単位での試験導入
新しい介護記録システムに強い反発がありましたが、1ユニットだけ先行導入しました。
そこで「入力が簡単になった」「ミスが減った」という声が自然に広がり、他ユニットも自発的に導入を受け入れるようになりました。
デイサービスの事例:目的の共有で納得感を得る
送迎ルート変更に対する反発は大きかったものの、利用者の安全という目的を共有し、現場の声を反映したことで反対意見は次第に減少。
むしろ改善提案が職員から出るようになりました。

グループホームの事例:小さな成果の見える化
新しい排泄ケアを導入した結果、1か月後に「転倒件数ゼロ」という成果が出ました。
それを全員に共有すると「やってよかった」という実感が生まれ、次の改革にも積極的に取り組むようになりました。
抵抗を味方に変える3つのステップ
- 目的と背景を丁寧に説明すること
- 小さな規模で試し、成果を見える化すること
- 職員の意見を取り入れて共に進めること
この3つを徹底すれば、抵抗は「改革を止める力」から「改革を支える力」に変わります。
明日からできる実践ステップ
次回改革を考えるときには、必ず説明会を開きましょう。
反対意見も否定せず傾聴し、成果が出たら数字や具体的なエピソードで共有します。
例えば「排泄介助にかかる時間が15分短縮された」と伝えるだけでも説得力が違います。
こうした小さな積み重ねが、介護現場改善の大きな力となります。
それでも「改革がまったく受け入れられない」「上司から挑戦を止められる」といった壁にぶつかることもあります。
特に40代以降の介護主任・管理者は「あと何年挑戦できるだろうか」と焦りを感じることも少なくありません。
そんなときは、思い切って介護職専門の転職エージェントを利用してみるのも一つの方法です。
現場裁量の大きい職場や、改革に前向きな経営者がいる施設を紹介してもらえれば、自分の力を存分に発揮でき、キャリアアップにも直結します。
 まとめ
まとめ
抵抗は避けるものではなく、扱い方次第で推進力になります。
リーダーは「目的の共有」「小さな成功」「職員参加型改革」を実践し、組織を一歩ずつ前に進めましょう。
次回(第6話)は「無駄を減らし成果を上げる会議運営術」というテーマを取り上げます。
ドラッカーの会議改革論を介護現場に応用する具体的な方法をお届けします。

よくある質問(FAQ)
Q1. 抵抗が強すぎて改革が止まってしまったら?
A. まずは立ち止まり、説明不足や情報不足が原因でないかを確認してください。多くの場合は「目的が共有されていない」ことが原因です。
Q2. 40代以降での転職は遅いのでは?
A. 決して遅くはありません。主任・管理者としての経験はむしろ評価されやすく、マネジメント経験を活かせる求人は増えています。
Q3. 改革提案が無視されます。どうすれば?
A. 組織文化や経営方針が根本的に合わない可能性もあります。その場合は転職で環境を変える方が、自分の力を生かせる選択となります。
引用書籍
- 『マネジメント[エッセンシャル版]』ダイヤモンド社
- 『イノベーションと企業家精神』ダイヤモンド社
コメント