介護の現場には、ちょっと不思議な法則があります。
仕事は寂しがり屋だから、忙しい人の所へやってくる。
朝礼が終わった瞬間から三方向同時コール――
そんな介護リーダーの“あるある”を、物語風に読み解きつつ、
部下への任せ方・育て方、そしてキャリアの広げ方まで一気に整理します。
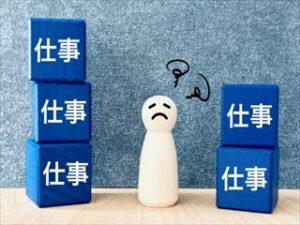
第一幕:忙しい人のところに、なぜ仕事は集まるのか
「佐藤リーダー」はなぜモテる?(仕事に)
「困ったら佐藤さんに聞こう」――そう思わせる人は、自然と仕事を呼び寄せます。
その理由はとてもシンプルです。
昔から「急ぎの仕事は忙しい人に頼め!」と言われます。
それは、なぜでしょうか?
- 先回りして動くから「この人なら安心」と思われる
- 笑顔で受け止めるから「声をかけやすい」と感じられる
- 返事が早いから「すぐ解決する」と信じられる
これらの行動は「頼んでも大丈夫」というサインになり、結果として仕事が集中してしまうのです。
なぜ“忙しい人”ばかりが大変になるのか
介護現場は一般企業とは少し違うかもしれませんが、ナースコールばかりでなく、どれもが優先業務とも思われるような突発的なアクシデントが多く、加えていつ終わるやも解らない事務作業。
そして何より恒常的な人手不足。
その中で「安心感のある人」に仕事が集中すると、一人に負担がのしかかり、燃え尽きの危険が出てきます。
言い換えれば、仕組みがないから“人”に偏っている状態です。
“人に集まる構造”を卒業する
ここから脱却するには、「佐藤さんなら安心」という思いを、人ではなく仕組みに移すことが大切です。
例えば…
- 当番・窓口の一本化(今日は誰に言えばいいかを明確にする)
- RACIで役割分担(誰が実行/誰が責任者かを一目でわかる表)
- テンプレとマニュアルを共有して、判断を「人任せ」にしない
仕組みが整うと、仕事は“人”ではなく“プロセス”に集まります。
これが、忙しい人だけが苦しむ地獄から抜け出す第一歩です。

仕事やプロジェクトの役割分担を明確にするためのフレームワークRACI(ラシ)の4つの役割
-
R(Responsible/実行者)
実際に手を動かして仕事をする人。
例:記録を書く、計画書を作る、報告書を提出する。 -
A(Accountable/最終責任者)
最終的にその仕事の結果に責任を持つ人。
基本的には一人だけ。
例:リーダーや管理者が、内容を承認する立場。 -
C(Consulted/相談・助言する人)
実行者が迷った時に相談する人。
例:看護師、ケアマネ、ベテランスタッフなど。 -
I(Informed/報告を受ける人)
進捗や結果を共有される人。
例:チーム全体や関係部署。介護現場での具体例
例えば「加算に必要な計画書作成」という仕事なら:
-
R:計画書を実際に作る介護職員
-
A:その内容を最終確認し、署名するリーダーや管理者
-
C:医師や看護師、ケアマネから必要な情報をもらう
-
I:チーム全員に「計画書を作成・承認済み」と共有
-

第二幕:仕事が寄りつかない人のサイン
頼まれにくい人の共通点
逆に「仕事を頼まれない人」という残念な人もいます。
その人に問題がなくても、次のような態度は「頼みにくい」と見なされがちです。
- 返事が遅い・曖昧(「了解しました」が言えない)
- 担当外をすぐ口にする(「自分には関係ない」と見えてしまう)
- 進捗や次の一手が見えない(「任せて不安」と思われる)
- 小さな工夫を発信しない(「成長が感じられない」と思われる)
30日で信頼を取り戻す“超・小さな行動”
そんな頼まれにくい人が信頼を得るには、難しいことをする必要はありません。
次のような小さな習慣を30日間続けるだけで、印象は大きく変わります。
- 3秒挨拶・3秒返事・復唱(「10時までですね」と確認するだけ)
- 昼と終礼に20秒の進捗報告(「今日ここまで終わりました」と数字で言う)
- 小改善をA4一枚で見せる(「ワゴンの配置を変えました」と写真付きで発信)
信頼は「一気」ではなく「積み上げ」でしか生まれない。
「任せてもらえる自分」になれば、役割も広がり、キャリアの選択肢も増えていきます。
第三幕:リーダーの「任せ方」と「育て方」
仕事を任せる前の要点を伝達するための7要素
目的/成果物/締切・中間チェック/品質基準/使ってよいリソース/連絡頻度・方法/エスカレーション基準
ちょっと難しいように感じますが、これを伝えてから任せるだけで、「やってみたけど違いました」というズレを防げます。
5段階で仕事を任せていく
- 指示型(手順通りにやる)
- 手順提示型(手順+目的を伝える)
- 結果基準型(目的・成果・締切・品質を明示)
- 自律型(戦略と配分も本人が決める)
- 権限移譲型(意思決定も本人に任せる)
最初は1〜2から始め、慣れてきたら3〜5へ。
少しずつレベルを上げていくのがコツです。
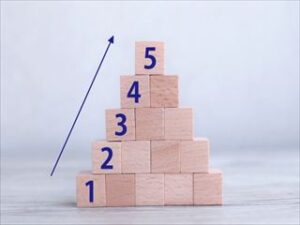
即効で効く簡単なフィードバック方法「NICE」
褒め方やフィードバックは長く語る必要はありません。
この4ステップだけ覚えておきましょう。
- Notice:気づいたことを伝える
- Impact:現場や利用者にどう良かったかを言う
- Continue:続けてほしい点を伝える
- Explore:次に挑戦してほしいことを提案する
第四幕:現場でそのまま使えまる会話テンプレ
任せるとき
「目的は返戻ゼロ。
3件を10/12までに。
品質は先月のテンプレ通り、指摘2点以内。
毎日16:45に進捗を2分共有。
迷ったら30分以内に日直へ。
――復唱お願いします」
頼まれにくい部下へのコーチング
「依頼の復唱と締切確認を必ずセットで。
今日の終礼で、自分の進捗を数字で20秒報告してみよう」

第五幕:キャリアを味方に
「任せる力」を伸ばしてチームで成果が出ると、外からの市場価値も上がります。
今の職場で挑戦できることが少ないと感じるなら、情報収集だけでも転職エージェントに相談してみるのも一つの方法です。
こんな人は早めに介護専門の転職エージェントに相談を
- 役職に対して裁量が小さい/評価が不透明
- 改善のアイデアを出しても通らない
- 夜勤や休日のバランスを調整したい
今の職場で仕組みを整えるのも、次の環境で裁量を広げるのも、選べる自分であることが何より安心につながります。
まとめ――“忙しさの質”は自分で選べる
- 仕事が集まるのは信頼の証。ただし仕組みで分散させることが大切。
- 頼まれにくい人は、即レス・復唱・可視化で信頼を取り戻せる。
- リーダーは任せて育てる。少しずつ段階を上げながら委ねる。
- キャリアは情報戦。定期的に相場観をアップデートする。
「仕事は寂しがり屋」。
でも、苦しむのは一人である必要はありません。
チーム全員に仕事を行き渡らせる工夫をしながら、自分自身の未来も選んでいきましょう。

コメント