会議で決めごとをしても守られない、続かない——。
介護現場で変革を起こしても、すぐに元もに戻って定着しない——。
特に40代以降の主任・管理者は、限られた人員体制の中で「どうすれば現場に負担をかけず、効率的で成果の出る会議ができるのか」という課題に直面しているのではないでしょうか。
会議は本来、情報共有や意思決定のための場であるはずなのに、やり方を誤れば「ただの時間の浪費」に陥ってしまいます。
前回(第5話:変革に対する抵抗を克服する方法)では、「目的の共有」「小さな成功体験」「職員参加型改革」で、現場の抵抗を味方に変える方法を解説しました。
今回はドラッカーの理論をベースに、無駄を減らし、成果を生む生産的な会議運営術を具体的にお伝えします。
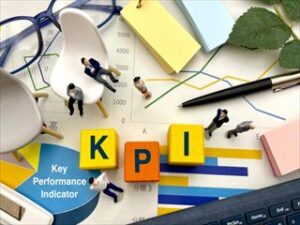
会議は「時間の投資」、必ず成果を残す設計を
ドラッカーは『経営者の条件』(ダイヤモンド社)でこう述べています。
「会議は時間の浪費であってはならない。成果を出すための場である」
つまり会議は「開催すること」が目的ではなく、「成果を残すこと」が目的です。
介護リーダーが会議を改革できれば、現場改善・人材育成・キャリアアップにも直結します。
目的のない会議は疲労だけ残す
ありがちな失敗例
介護現場では、
「何を決めるのか分からない会議」
「脱線して長引く会議」
「結論が出ないまま終わる会議」
が繰り返されがちです。
こうした会議は職員の集中力を奪い、リーダーへの信頼も低下させます。

私の体験談
以前、老健で月例の主任会議を担当した際、議題が曖昧で「結局何を決めたのか分からない」という不満が噴出しました。
そこで数日前には「介護の議題」を事前に伝えておき、さらに「この会議は何を決めるのか」を冒頭で宣言し、各議題をゴールとセットで提示しました。
その結果、会議の時間が短縮されるとともに、「やるべきことが分かりやすい」とスタッフ間にも周知されるようになりました。
介護現場の会議は特に時間が貴重
介護現場では会議に参加する=その間、現場の人手が減るということです。
会議が長引けば、利用者へのサービスに影響します。
「短時間で結論を出す」ことは、リーダーとしての責任であり、職場改善にも直結します。
実際の現場感覚
私がデイサービスで主任をしていた時、事前に議題を伝えておくことにより、リーダー会議を60分から30分に短縮しただけで、現場から「その分、利用者に目が届く」と感謝されました。
会議効率化はスタッフのモチベーション向上にもつながるのです。

ドラッカー流「生産的な会議」の条件
ドラッカーは『マネジメント[エッセンシャル版]』(ダイヤモンド社)で、効果的な会議の条件を整理しています。
- 目的を明確化する(情報共有/意思決定/問題解決)
- 議題を事前に共有する(何を話し、何を決めるか)
- 終了時に成果を確認する(誰が、何を、いつまでに)
私の応用事例
老健での会議案内メールに先述の議題に加え、「目的・所要時間」を必ず記載するルールを加えて導入しました。
その結果「今日はこの結論を出すんだな」と参加者の意識が揃い、会議時間が半分に短縮しました。
会議改革で変わった現場
事例1:15分スタンディング会議
あるデイサービスでは、毎朝のミーティングを立ったまま行いました。
目的は「前日の振り返り」と「当日の注意点共有」に絞り、タイマーを使って10分で終了。
結果として「だらだら感が消えた」「現場のテンポが良くなった」という声が上がりました。
事例2:議題ごとに担当を設定
特養の主任会議では、議題ごとに担当者を決め、資料は事前に配布しました。
会議中に資料を読む時間をなくしたことで、平均30分の短縮に成功しました。
事例3:結論と担当をその場で決定
あるグループホームでは「会議終了5分前に決定事項・担当・期限をホワイトボードに書き出す」ルールを導入しました。
これにより「結局どうなったの?」という混乱がなくなり、実行率が大幅に上がりました。

まとめ ― 会議改革の3つのカギ
- 目的を明確化する(情報共有/意思決定/問題解決)
- 議題を事前に共有する(何を話し、何を決めるか)
- 終了時に成果を確認する(誰が、何を、いつまでに)
紹介した事例は、何も難しいことではありません。
この3つを押さえれば、会議は「時間の浪費」から「キャリアアップにつながる成果の場」に変わります。
すぐにできる介護の内容を周知する実践ステップ
会議案内に「目的・議題・所要時間」を必ず明記する
各議題の担当者を事前に指名する
会議後すぐに要点だけの議事録を配信する
もし「会議が長い」「結論が出ない」と変えられずに悩んでいるなら、改善が進んでいる職場に転職するのも選択肢です。
介護職専門の転職エージェントなら、
- 会議や運営の効率化を重視する法人
- 働き方改革を積極的に進めている職場
を紹介してもらえます。
会議に振り回されるのではなく、成果を出せる環境でキャリアを積むことが可能です。
まとめと次回予告
会議の質はリーダーの設計力次第です。
限られた時間を最大限活かし、参加者全員が「やってよかった」と思える会議に変えていきましょう。
次回(第7話)は「離職防止と職員定着の戦略」をお届けします。
ドラッカーのマネジメント視点から、職員が長く働き続けたくなる職場づくりを解説します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 会議を短縮すると重要な情報が抜けないか不安です。
A. 議題を絞り、資料を事前配布することで、情報不足は防げます。重要事項だけに集中する方が実は効率的です。
Q2. 40代以降で転職を考えても遅くないですか?
A. むしろ主任・管理者としての経験は評価されやすく、転職市場での需要は高まっています。
Q3. 会議効率化の提案が無視されます。どうすれば?
A. 組織文化が合わない可能性があります。その場合は効率的な運営が根付いている職場に転職するのも有効です。
引用書籍
- 『経営者の条件』ダイヤモンド社
- 『マネジメント[エッセンシャル版]』ダイヤモンド社
コメント