「リーダーとして経営者目線で考えなさい」
多くの職場で耳にするアドバイスですが、この言葉はしばしば誤解を生むこともあります。
リーダー職に就いてつい、気負ってしまって“何でも自分で決めて指示を出さなければいけない”とか、“現場を無視してでも経営だけを見ることだ”と勘違いしまうことにあるようです。
特に介護・福祉の現場では、ご利用者は高齢者や障がいを持つ方々です。
日々のサービス提供やクレーム対応、突発的なトラブル処理に追われる中で、「経営者目線で考える余裕なんてない」と感じるリーダーやサブリーダーも少なくないのではないでしょうか。
今回は、リーダーに求められる「経営者目線」の正しい捉え方と、目標をクリアするための論理的思考法を、具体的な現場事例を交えて丁寧に解説します。

「経営者目線」の本当の意味とは?
全体最適を意識する
経営者目線の第一歩は、個々の善意や担当視点の“部分最適”ではなく、組織全体の成果=全体最適を選ぶことです。
事例A:機能訓練“10分延長”で送迎が崩れる
あるデイサービスで、機能訓練指導員が「効果を高めたい」と自主的に10分延長を継続。
1名ずつの延長は善意ですが、1日全体では総遅延が60分超に。
帰りの送迎が押し、家族からの不満が増加しました。
- 観点転換:「この10分は、全体にとって最適か?」を常に問う。
- 代替策:延長は評価週のみに限定し、通常週はメニュー密度を上げる(待機時間の圧縮、同時進行の工夫)。
- 効果測定:送迎定時率、家族満足度、機能維持スコアを月次で可視化。
結果、送迎定時率は92%→99%へ改善。訓練効果は維持しつつ、全体満足を底上げできました。
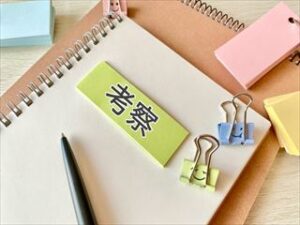
数字で考える(感覚→事実)
「忙しい」「大変」は主観です。経営者目線では計測・記録・可視化で“事実”に変換します。
事例B:入浴介助の「しんどい」を分解
職員の訴えは「入浴がしんどい」。
作業工程を動画とタイムで可視化すると、実際の負荷源は更衣室の渋滞(待機7分)とタオル・替え衣類の探索(2分)でした。
- 更衣前準備ステーションを設置(衣類セット化・サイズ別トレー)。
- 「前処理係」を固定配置し、入浴ラインに入る前に準備完了状態を作る。
- 使用済みタオルのワンウェイ動線を設定し、バックフローを防止。
効果:1人あたり平均25分→17分、ピーク時渋滞ゼロ、昼食提供の定刻率向上。
未来から逆算する(バックキャスト)
「今できること」から考えるのではなく、あるべき姿(3か月後・1年後)を先に定義し、逆算して今日の行動を決めます。
事例C:満足度一時アップの“豪華食”が持続不能に
短期的な満足を優先し、食材費を上げたところ、数か月後にコスト増と期待値固定が発生。バックキャストで「1年継続可能な栄養・嗜好・コストの最適点」を設計し、季節行事にメリハリを付ける方針へ。満足度を維持しつつ、コストを標準域に戻せました。

リーダーが陥りやすい誤解
「自分が全部決める」が正解ではない
独断専行は短期的スピードは出ますが、チームの判断力を奪います。
判断基準(目的・安全・時間・コスト)を共有し、現場に委ねる範囲を意図的に増やしましょう。
現場軽視ではない
数字だけ追うと安全や尊厳を損ないます。
経営者目線は、現場の声 ⇄ データの翻訳者になることです。
クレーム処理だけで終わらせない
謝罪で終わると再発します。
原因特定 → 対策 → 標準化 → 監視KPIまで運ぶのが経営者目線です。
目標達成のための論理的思考ステップ
ステップ1:目的を明確に(Why)
同じ「送迎見直し」でも、時間短縮が目的か安全性向上が目的かで解は変わります。
目的→評価基準→代替案の順で設計します。
ステップ2:事実と意見を切り分ける
「遅い」は意見、「平均遅延15分」「95%点で28分遅延」は事実。
事実テーブルを先に作ると、議論が前に進みます。
ステップ3:仮説→小さく試す→検証(PDCA)
いきなり全体導入せず、一部ルート・一部時間帯でテスト。
効果があれば展開、なければ撤回。
ステップ4:再現性のある仕組みに落とす
属人的工夫で終わらせず、SOP・チェックリスト・教育に落とし込む。
人が変わっても結果が出る状態が「仕組み化」です。

介護現場での実践例
事例1:入浴介助の時間管理を“工程設計”で解決
状況:昼食が毎日15分遅れる。原因は入浴工程の滞留。
調査:各工程(待機・脱衣・洗身・洗髪・移乗・整容)をタイムスタディ。
脱衣所前の渋滞と物品準備の分散がボトルネックと判明。
- 対策① 役割の同時並行化:「前処理(更衣・タオル準備)」「洗身」「整容」の3ロールを固定、ラインを止めない。
- 対策② 動線の一方通行化:使用済みタオルの回収動線を片道に限定。
- 対策③ 記録の後工程移動:即時紙記録をやめ、バッチ入力(終了後5分でまとめて)。
- 対策④ 早見表:皮膚脆弱/転倒歴/補助具の注意ラベルで介助速度のムラを予防。
成果:平均25分→17分、渋滞ゼロ、昼食定刻率が94%→100%。職員アンケートの「入浴の負担感」は5段階で3.8→2.6に低下。
事例2:送迎遅延クレームを“データ×広報”で沈静化
状況:家族から「送迎が遅い」。謝罪対応が常態化。
調査:GPSログで遅延地点を把握。特定交差点の渋滞と、ルート順序の非効率が原因。
- ルート二刀流:通常ルートと渋滞回避ルートを用意、当日朝に切替。
- 出発10分前倒し+乗車前準備の標準化:靴・上着・持ち物を前夜チェックリスト化。
- 家族広報テンプレ:「遅延時の想定と連絡ルール」を事前合意し、期待値を調整。
- 週次レビュー:平均遅延・最大遅延・苦情件数を可視化し、改善サイクルに組み込む。
成果:平均遅延15分→3分、最大遅延30分→12分、苦情は月12件→2件へ。
スタッフの心理的負担も軽減。
事例3:排泄介助のピーク分散で“待たせない”を実現
状況:15:30〜16:30に呼出し集中、待機が長く不満が増加。
調査:コールログと対応タイムを抽出、ピークが特定。
- 対策① ピーク時だけ増員:本業務の閑散帯から60分の時限応援を配置。
- 対策② 事前声かけ:ピークの30分前に分散誘導、整容とセットで回遊。
- 対策③ 個別計画:頻尿・失禁リスクの高い方は個別スケジュールを見える化。
成果:平均待ち12分→4分、関連苦情ゼロ。転倒ヒヤリハットも減少。

リーダーに必要な「二重の視点」
リーダーには「現場を回す視点」と「全体を設計する視点」の両立が求められます。
現場理解があるからこそ、数字や仕組みに翻訳できる。
つまり、あなたこそが“現場と経営をつなぐ橋”です。
まとめ ― 経営者目線を武器にする
- 全体最適を選ぶ(部分善より全体善)。
- 数字で判断する(感覚→事実)。
- 未来から逆算する(持続可能性を優先)。
- 仕組み化で定着させる(SOP・チェックリスト・教育)。
これは「厳しく管理する技術」ではなく、論理的に考え、未来へつなげる判断力です。業務に追われる日でも、一歩引いて全体を見渡す視点を持てば、利用者満足と組織成長は両立できます。
Q&A ― よくある疑問
- Q1. 経営者目線で考えると、現場を軽視してしまわないか不安です。
- A. 軽視ではなく、現場の声を数字と方針に翻訳するのが経営者目線です。
- 現場の体感→簡易計測(時間・件数)→意思決定へ橋渡ししましょう。
- Q2. データを取る余裕がありません。最低限なら何を取れば?
- A. まずは時間(所要分/遅延分)と件数(介助回数/苦情件数)だけで十分。
- 週次で合計・平均を見るだけでも改善点が浮かびます。
- Q3. クレーム対応で手一杯のとき、どうすれば“仕組み化”まで行けますか?
- A. 対応後に30秒メモ(原因・対策・誰がいつやる)を必ず残し、週1レビューで3件だけ前進させるルールに。
- 小さくても積み上がります。
- Q4. 任せると失敗が怖いです。どこまで委ねれば?
- A. 基準と枠を明示し、失敗の影響範囲を限定(1ユニット・1日など)。
- 小さく試してレビューをセットにすれば、学びは大きくリスクは小さく保てます。
- Q5. 未来から逆算すると、現場の負担が増えるのでは?
- A. 逆算設計の要は持続可能性。負担増が出るなら「やらないことリスト」や作業の統廃合で相殺し、総負荷を増やさないのが原則です。
コメント