「新人が入っても、ベテランと噛み合わずにすぐ辞めてしまう…」
「世代間ギャップで職場の雰囲気がぎくしゃくする…」
「改善提案は出るけれど、実行に移す前に空中分解してしまう…」
こんな悩みはありませんか?
もしあなたが介護リーダーとして、こんな悩みを感じているとしたら、それは「ベテランと新人の強みを融合する仕組み」が不足しているのかもしれません。
前回(第19話:失敗を次の一手に変えるフィードバック術)では、失敗を学びに変える方法をご紹介しました。
今回はその続編として、ベテランと新人が互いの力を引き出し合うチームづくりの具体的な方法を解説します。

【結論】ベテランと新人の融合が介護現場の成長を加速させる
介護現場では、経験豊富なベテランと意欲あふれる新人が混在します。
しかし、両者の強みが活かされずに摩擦だけが生じてしまうと、離職や不満につながります。
結論として言えるのは――
「ベテランと新人が互いの強みを活かす仕組みを作れば、現場は持続的に成長し、離職率も低下する」
ということです。
【理由1】ベテランの強みは「経験知」と「暗黙知」
長年の経験が培う判断力の差
聞きなれない言葉が並びましたが、ベテラン職員は、何十年と現場を経験する中で「教科書やマニュアルに載っていない判断力」を培ってきました。
例えば、利用者が表情を変えただけで体調の変化を察することや、事故を未然に防ぐ勘。これは一朝一夕では身につきません。
脳科学から見た「成功の記憶」
西田文郎氏の『勝負脳の鍛え方』(講談社)では、経験によって培われた判断は「成功の記憶」を活かす脳の働きだと説明されています。
つまりベテランは、過去の成功体験を瞬時に引き出せる能力を持っているのです。

【理由2】新人の強みは「柔軟性」と「新しい発想」
固定観念がないからこその視点
新人は「業界の常識」に縛られず、自由な発想で改善策を提案できます。
例えば「タブレットで記録を共有した方が効率的では?」といった発言は、ベテランだけの現場ではなかなか出にくい意見です。
最新知識の持ち込み
新人は、直近の研修や資格取得で学んだ最新知識を現場に持ち込みます。
これは現場のアップデートに直結し、「現場力の鮮度」を保つ役割を担っています。
【理由3】相互学習が組織力を高める
双方向で学び合う
「ベテランが新人を育てる」だけでは片手落ちです。
新人もまた、ベテランにICTや新しい介護手法を伝えられます。
この「双方向の学び」があると、職場全体が進化していきます。

【私の体験談①】新人との衝突を「逆メンター制度」で乗り越えた
悩み:ICT導入に抵抗するベテラン
私の勤務していた特養では、記録をタブレットに移行しようとしました。
しかし、ベテラン職員からは「紙の方が安心」と猛反発。
新人は「タブレットの方が効率的」と主張し、完全に対立しました。
【改善策】逆メンター制度
そこで導入したのが「逆メンター制度」です。
(※メンター制度は、病院系の施設であれば「プリセプター制度」と呼ばれていることが多いようです。)
ベテランが新人に現場判断力を教え、新人がベテランにタブレット操作を教える時間を設けました。
【成果】
最初はぎこちなかった関係も、やがて「教え合う空気」が生まれました。
結果として、記録業務の時間が1/3に短縮。さらに「ベテランもまだ学べる」という気づきがあり、雰囲気が柔らかくなりました。
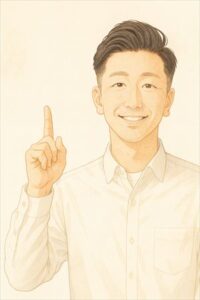
【私の体験談②】ペアケアで新人の定着率が劇的に改善
【悩み】新人がすぐ辞める
以前デイサービスでリーダーをしていた頃、新人が入っても「任されすぎて不安」「誰に相談すればいいか分からない」といった理由ですぐ辞めてしまう状況が続きました。
【改善策】ペアケア制度
そこで、日替わりでベテランと新人をペアにして業務を担当。
新人には「一人じゃない」という安心感を、ベテランには「新しい発想を学べる機会」を提供しました。
【成果】
この仕組みで新人の定着率が大幅に改善。3か月以内に辞めてしまうケースがほとんどなくなり、ご利用者の満足度アンケートも10ポイント以上改善しました。

【具体例】他施設での成功事例
グループホームの「改善ワークショップ」
月1回、全員参加で業務改善ワークショップを実施。
新人が自由に提案し、ベテランが「現実的に実行可能か」を判断。
結果として採用率が高まり、スタッフ全員が「自分の意見が反映される」と感じられる現場になりました。

【実践方法】ベテランと新人の融合を進める3つの仕組み
1. 双方向メンター制度
・ベテラン → 新人:現場対応力の伝授
・新人 → ベテラン:最新技術や効率化ノウハウの共有
2. ペア業務の導入
・日替わりでペアを組み、交流と学びを促進
3. 月1回の改善会議
・立場に関係なく意見を出し合える場を設ける
<※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。>
「今すぐ辞めるわけじゃないけど、転職も頭をよぎる…」
そんな気持ちを抱いていませんか?
現場でスキルを積み上げたい気持ちと、
「もっと自分に合った職場があるのでは?」という不安。
どちらも自然なことです。
そんなときは、転職エージェントに事前相談だけしておくのがおすすめです。
今後のキャリアプランを整理したり、いざという時に動けるように情報収集しておくだけでも安心です。
🔗 \無料登録5分/ 介護職専門の転職エージェントに今すぐ相談<PR>
 まとめ ― 多様性がチームの原動力
まとめ ― 多様性がチームの原動力
経験と新鮮な視点は、本来対立するものではなく補い合うものです。
リーダーが橋渡し役を担い、仕組みを整えることで、現場はより柔軟で強い組織へと成長します。
次回は、第21話:「逆境を力に変える」勝負脳の鍛え方 という話題でお届けします。
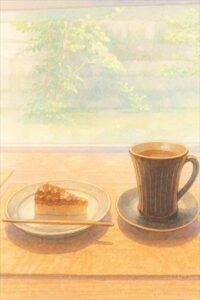
【よくある質問(FAQ)】
Q1. 新人とベテランの摩擦が強い場合、まず何から始めれば良いですか?
A. まずは「ペアケア」から始めるのが最も効果的です。日替わりで組むだけで互いを理解するきっかけが生まれます。
Q2. 双方向メンター制度は小規模事業所でも可能ですか?
A. 可能です。小規模ほどコミュニケーションが密になりやすく、導入効果は大きいです。
Q3. 改善ワークショップを開いても意見が出ないのですが?
A. 「匿名意見BOX」や「事前アンケート」を活用することで、発言しやすい仕組みを作れます。
仕組みさえ整えば、世代や経験の違いはチームの強みに変わります。
________________________________________
【引用書籍リスト】
• 『勝負脳の鍛え方』 西田文郎 著/講談社
• 『No.1理論』 西田文郎 著/サンマーク出版
________________________________________
コメント