前回の記事では、「できたこと」にフォーカスすることで脳が活性化し、チームのポジティブ回路が育つというテーマを取り上げました。
今回は、その“前段階”にある「失敗」について深掘りします。
介護現場では、転倒、誤薬、情報共有の不足など、誰もが一度はヒヤッとする体験があります。
しかし、それを“失敗”として終わらせてしまうのか、“成長”に変えるのかで、現場の未来は大きく変わります。
キーワードは「脳の進化」です。
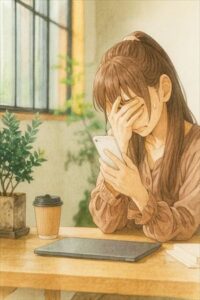
失敗は“脳の進化スイッチ”
失敗は、チームと自分を進化させる貴重な「脳トレ」の機会
西田文郎氏は著書『ツキの最強法則』(現代書林)で、「脳は失敗によって学び、成功によって確信を得る」と述べられています。
つまり、失敗なくして進化はないのです。
「失敗=マイナス」ではなく、「失敗=進化のサイン」と捉えることが、リーダーの視座(考え方)として求められます。

なぜ、失敗が脳にとって“財産”になるのか?
シナプス可塑性が働くタイミング
人間の脳には「シナプス可塑性(かそせい)」という機能があります。
これは、経験や環境に応じて脳の神経回路が柔軟に書き換えられる仕組みのこと。
特に“失敗”をしたとき、脳は「なぜうまくいかなかったのか?」を無意識に分析し始めます。
その分析こそが、次の「成功パターン」につながるのです。
事例①:現場が変わった!失敗からの好転事例
デイサービスでの「転倒事故」とチーム改善
あるデイサービスで、ご利用者が入浴介助中に転倒してしまう事故が発生しました。
担当の職員は深く落ち込み、「自分のせいだ…」と責任を抱え込みました。
そこで主任は、“個人を責めない”という前提で、事故の要因をチームで検討。
• マットの位置がずれていた
• 声かけが不十分だった
• 利用者が前日に睡眠不足だった
こうした要因が複合的に絡んでいたことが判明し、次のアクションが取られました。
• 入浴介助のチェックリスト作成
• 朝礼での状態共有ルールの明確化
• 声かけ研修の導入
この結果、類似の事故はゼロに。
職員も「やってはいけない」から「こうすれば防げる」に思考が変わったのです。
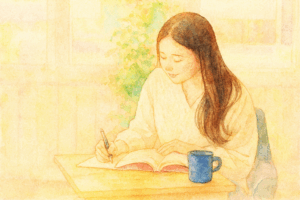
事例②:現場が変わった!失敗からの好転事例
ショートステイでの「情報伝達ミス」と言葉の力
夜勤者が利用者の“食事制限”を把握しておらず、誤って通常食を出してしまう事故がありました。
そこでリーダーが取った行動は、
• 「なぜミスが起きたのか?」の共感的ヒアリング
• 「申し送りの言い方・タイミング」の見直し
• ホワイトボードによる視覚的共有の強化
また、朝礼では「ありがとう、昨日の共有助かりました」という感謝の言葉を意識的に使うことで、共有の空気が格段に良くなりました。
西田文郎氏は『脳が認める勉強法』(現代書林)で「感謝の言葉が脳を報酬で満たし、前向きな行動を誘発する」と述べています。
まさにその実例です。
事例③:現場が変わった!失敗からの好転事例
「新人潰し」を防いだ先輩職員のひと言
これもあるデイサービスでの出来事です、
先輩職員の指導が厳しく、新人が辞めてしまうケースが続出していました。
そこで主任が実施したのが、「新人の観察ノート」の導入です。
さらに、あるベテラン職員が新人にこう伝えたのです。
「最初から完璧にできる人なんていないよ。私もミスしてここまで来たから、大丈夫」
この一言で、新人は見違えるように自信を取り戻しました。
その後、新人職員が研修会で堂々と発言するまでに成長。
言葉の力が、「負けグセ」から「勝ちパターン」へのシフトを実現した好例です。

挑戦し続けるあなたに、次のステージを
<※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。>
失敗を恐れず挑戦を続けるあなたのようなリーダーを、必要としている職場はたくさんあります。
今の職場で得た経験を活かし、新たなキャリアに踏み出したい方は、以下の介護専門の転職支援サービスをぜひご活用ください。
【介護職専門の転職サポートはこちら】
「負けグセ」から「勝ちパターン」へ
失敗するたびに落ち込むのではなく、
「次に成功するためのヒントがまた一つ手に入った」
という思考に切り替えていくことが、介護現場において最強のメンタルトレーニングとなります。
リーダー自身がこのマインドセットを持ち続けることで、職員も失敗を恐れず、挑戦と改善を繰り返す職場へと進化していくのです。

まとめ 失敗を「宝」に変えるリーダーシップ
職場に漂う“失敗への恐怖”は、職員の自発性や学びの機会を奪ってしまいます。
ですが、リーダーが「失敗=進化のサイン」として捉え直すことで、職場は劇的に変わります。
• 責めるのではなく仕組みで防ぐ
• 落ち込むのではなく言葉で支える
• 指摘するのではなく一緒に考える
こうした習慣が、失敗を「宝」に変える文化をつくるのです。
次回予告
次回は、第9話:「やらされ感」を消すには“目的の言語化”という話題です。
「やらされてる感じがしてモチベーションが上がらない…。なぜ人は意味が見えないと行動しないのか?」という悩みにお答えします。
行動の裏側にある“意味”を言語化することで、現場がどう変わるのか?
西田文郎理論と実例を交えて解説しますよ(^^♪
________________________________________
【参考文献|西田文郎氏の著書】
• 『ツキの最強法則』(現代書林)
• 『脳が認める勉強法』(現代書林)
• 『NO.1理論』(サンマーク出版)
• 『リーダー脳のつくり方』(現代書林)
コメント